筋トレと炭水化物の正しい関係|増量・減量を成功させる食事戦略と摂取タイミング

皆さん、こんにちは!!トレーナーのYUKIです。
本日は、炭水化物がもたらす筋トレのメリット、デメリット・増量、減量の炭水化物の摂取方法についてお話ししていこうと思います!
炭水化物とは・筋トレとの関係性
まず簡単に炭水化物の役割を整理します。炭水化物は、グルコース/グリコーゲン(筋グリコーゲン・肝グリコーゲン)として貯蔵され、運動時の主なエネルギー源となります。一般的には持久運動(エンデュランス)分野での研究が豊富ですが、近年では抵抗トレーニング(重量挙げ・筋肥大)との関係も注目されてきています。例えば「スポーツ栄養学」分野のレビューで、抵抗トレーニング/筋力トレーニングにおけるCHOの効果を整理したものもあります。
この前提を踏まえて、次に「メリット・デメリット」を整理します。
炭水化物のメリット(筋トレにおいて)
炭水化物摂取が筋トレに対してプラスに働る可能性のある側面を、具体的に論文と共に見ていきましょう。
グリコーゲン補填・トレーニング強度維持
炭水化物を適切に摂ることで、筋・肝グリコーゲンが維持され、トレーニング中のエネルギー枯渇を防ぎ、強度・ボリューム(セット数×反復回数)を維持しやすいという報告があります。
例えば、レビューでは「筋トレ中に炭水化物摂取は、ボリューム性能(セット数・出来る反復回数)を向上させうる」と記されています。
また、筋グリコーゲン低下後の回復時に、炭水化物補給が回復を促すという観点も。
体組成・筋肥大支援の可能性
筋トレ+適切なエネルギー・栄養摂取の環境下では、少し高めの炭水化物摂取が筋肥大(除脂肪体重増加)に好影響を与えたという研究もあります。例えば、ある研究では12.9 g/kg体重/日という高CHO群が8.0 g/kg体重/日群より筋量増加が大きかったという報告が出ています。
このことから、「筋量を増やしたい・強度を高めたい」目的には、炭水化物をしっかり確保することが有効な戦略のひとつとなり得るわけです。
回復促進・筋グリコーゲン再合成
トレーニング後の回復期において、炭水化物を摂取することで筋グリコーゲンの再合成が促進され、次のトレーニングに向けて準備が整いやすくなります。例:メタ分析では、CHO摂取は非栄養プラセボに比べて筋グリコーゲン再合成率を有意に高めたと報告されています。
そのため、特に高頻度トレーニング、複数部位・高セット数・みっちりやる人ほど、この恩恵が大きいと考えられます。
炭水化物のデメリット(筋トレにおいて)
もちろん、炭水化物を摂ることには注意すべき点もあります。筋トレ目的での取り扱い上、知っておくと役立つデメリットを整理します。
摂りすぎ・総エネルギー過多のリスク
炭水化物を多く摂るということは、必然的に総エネルギー摂取も増やしやすく、特に増量期でなければ体脂肪増加(余剰カロリー)につながる可能性があります。実際、ある大規模コホート研究では、1日あたり100 gの澱粉または糖分の増加が4年で体重増加を伴ったという報告があります。
つまり「炭水化物=ただ良い」というわけではなく、エネルギーバランス・質・タイミングが重要です。
回復・筋合成への直接的効果が必ずしも強くない
興味深いのは、たとえば「スポーツ栄養学」のレビューによると、タンパク質を十分摂取している状況下で、さらに炭水化物を付け加えたからといって、筋タンパク合成量は明確に増えるという十分な証拠がない、というものがあります。
また、抵抗トレーニングにおいて「トレーニング10セット/部位程度以下の通常のボリューム」であれば、炭水化物摂取の量・影響はそんなに明確ではない(負荷が限定的な場合)という報告もあります。
炭水化物制限(低CHOまたはケトジェニックなど)との兼ね合い
一方で、炭水化物を大きく制限した低CHO食/ケトジェニック食が筋力・筋量維持・脂肪減少の観点で「有効になる場面」もあります。例えば、体脂肪を落としたい減量期において「エネルギー制限下での低炭水化物」が筋量維持・脂肪減少の戦略として報告されています。
ただし、ここでトレーニング・栄養・回復の条件を慎重に整えないと、逆に筋量の低下/回復力低下というリスクもあるため、「状況を見極めた上で選択」すべきです。
増量期における炭水化物摂取の仕方
次に、「増量期(筋肥大・筋量アップを目的としたエネルギー+栄養+トレーニング期間)」において、炭水化物をどう摂るかという戦略を、論文をもとに整理します。
増量期の目的・前提
増量期の基本目的は「筋力トレーニングでの刺激を最大化」「筋タンパク合成を促進」「筋グリコーゲン・エネルギー貯蔵を十分に維持」「回復を促進」「そして可能な限り余剰カロリーを筋量増加(除脂肪体重増)に振り向け、脂肪増加は最小化」という点です。
この目的を達成するには、総エネルギー摂取量が消費量を上回る(エネルギー収支がプラス)且つ、タンパク質・炭水化物・脂質のバランスが重要です。
炭水化物量・摂取目安
筋肥大を目的とした研究では、比較的高めの炭水化物摂取が除脂肪体重増加に貢献したというものがあります。例えば、前述の研究では12.9 g/kg体重/日というかなり高い摂取量で、8.0 g/kg体重/日の群より筋量増加が大きかったという報告があります。
ただし、これはかなり条件が恵まれたトレーニング+栄養管理下の被験者・短期研究であるため、すべての人がこの量を必要とするわけではありません。
現実的な指標として、「トレーニング日には体重×4〜7 g/kg体重/日」レベルを炭水化物目安とするトレーナー・栄養士のケースは多いです(ただし研究的な指標が定型化されているわけではありません)。また、トレーニング量が多い(セット数・頻度・部位が多い)ほど、炭水化物需要も上がる可能性があります。
時間・タイミング戦略
増量期には、トレーニング前/中/後の炭水化物摂取も有効です。特にトレーニング前にある程度の炭水化物を摂ることで、トレーニング中の強度低下を防ぎやすくなります。研究レビューでも「トレーニング開始前3時間以内に少なくとも15 g程度の炭水化物+0.3 g/kg体重のタンパク質を摂るのが良い」という提案もあります。
トレーニング後は、筋グリコーゲン回復・タンパク質合成促進のために、炭水化物+タンパク質を摂るのが常套戦略です。例えば「炭水化物3〜4 g:タンパク質1 g」比率が提案されることがあります。
実践的ポイント
• トレーニング前食:例えば 体重×1〜2 g程度の炭水化物(重トレ60~90分前)+少量のタンパク質。
• トレーニング中/直後:高セット数・複数部位の場合は、筋グリコーゲンを枯渇させないために、炭水化物10〜30 g/時間程度を補給する例もあります。
• トレーニング後食:炭水化物を “体重×1〜2 g” 程度+タンパク質(体重×0.3 g〜0.4 g)を30〜60分以内に摂ると回復・筋合成をサポートしやすいです。
• 日常合計:除脂肪体重維持+筋量増加を目指すなら、炭水化物+タンパク質+脂質のバランスを整えつつ、エネルギー収支がプラスとなるよう調整すること。
• 質の確保:精製された砂糖・白パン・菓子といった「速い炭水化物」は急速に血糖値を上げやすいため、全体としては「玄米・全粒粉、芋類、果物、野菜」などを中心に、トレーニング直前/中は速吸収タイプも戦略的に使うというメリハリが有効です。
減量期における炭水化物摂取の仕方
次は「減量期(脂肪を落としつつも、できるだけ筋量を維持・あるいは増やそうとする期間)」における炭水化物の戦略です。
減量期の目的・前提
減量期では「総エネルギー摂取量を消費量より下回らせる(エネルギー収支がマイナス)」ことが基本です。その中で、筋量低下を最小化し、トレーニング強度・頻度を維持できることが鍵です。そして、炭水化物はトレーニングを支えるエネルギー源としての役割を担うため、減量期でも侮れない栄養素です。
炭水化物量・摂取目安
減量期は炭水化物量を少し抑える傾向にありますが、過度に減らすとトレーニング強度低下・筋量低下・回復遅延を招くリスクがあります。レビューでは「低炭水化物食は脂肪減少には有効だが、筋量維持・トレーニング強度維持という観点では慎重を要する」とされています。
例えば、日常的に体重×3〜5 g程度を炭水化物の目安とし、トレーニング量が多ければ少し上、量が減れば少し下というような調整が現場ではよく用いられます。
時間・タイミング戦略
減量期には、
• トレーニング前:エネルギーが減っている状態でも強度を落とさないため、少量の炭水化物(例:20〜40 g)+タンパク質をトレーニング60分前に摂る。
• トレーニング直後:筋グリコーゲン回復+筋合成支援のため、やや控えめの炭水化物+しっかりタンパク質(体重×0.3〜0.4 g)を。
• 日中・練習以外時間:炭水化物摂取量をトレーニング量に応じて調整し、休息日や低負荷日には炭水化物量を少し下げる「デイリーの炭水化物量変化(いわゆる炭水化物周期化/Carb cycling)」戦略を使うこともあります。
たとえば、高強度トレーニング日=炭水化物多め、軽トレ日や休養日=炭水化物少なめというメリハリです。こうした戦略は、脂肪減少と筋量維持・トレーニング強度維持のバランスをとるために有効とされています。
実践的ポイント
• トレーニング日の炭水化物は「体重×3〜5 g」程度を出発点に、負荷/セット数が多ければ「+」する。
• 休養日・軽負荷日には、「体重×2〜3 g」程度に抑えても良い。
• 炭水化物を減らす際には、タンパク質量(体重×1.6〜2.2 g等)と脂質量を適切に保ち、エネルギー摂取そのものが過度に低下しないようにする(筋量低下防止のため)。
• 質を重視:減量期では、血糖値変動が激しい精製炭水化物(砂糖・白パン・スナック)を控え、食物繊維・低GIの食品を中心に摂ると満腹感も得やすく、過食リスクも下がります。
• モニタリング:体重・体脂肪率・筋力(1RM・セット数維持)を定期的にチェックして、「炭水化物少なすぎてトレーニング強度落ちてるな」「筋量減少してるな」と感じたら、炭水化物量を微調整すること。
増量/減量期共通で押さえるべき炭水化物戦略
ここでは、どちらのフェーズでも大切な炭水化物摂取戦略のポイントを整理します。
• エネルギー収支を意識する:炭水化物量を決める前に、まずその日の総エネルギー摂取量・消費量を見て、「収支がどうなってるか」を把握することが前提です。
• トレーニング量・頻度・強度と炭水化物需要が比例する:高頻度・高セット数・高強度のトレーニング日には、炭水化物の摂取量を増やす必要があります。逆に低頻度・軽負荷の日は少なくても問題ない(むしろ脂肪管理目的なら少なめでも良い)です。
• タイミングを活用する:トレーニング前・中・後の炭水化物摂取を戦略的に使うことで、回復支援・筋合成促進・トレーニング強度維持に繋がります。
• 質を選ぶ:量だけでなく、どの炭水化物を選ぶか(全粒穀物、芋類、果物、野菜、低GIスイーツなど)も重要です。特に減量期には、血糖値の急上昇・急下降を避け、満腹感・栄養価を兼ね備えた良質炭水化物へシフトする方が賢明です。
• 個人差・調整性を持たせる:体重・体脂肪・筋量・消化能力・トレーニング歴など個人差があります。研究値はあくまでも「目安」であり、実践では体調・トレーニング感・体組成変化を観察しながら微調整をします。
• タンパク質・脂質とのバランスを忘れずに:炭水化物を意識するあまり、タンパク質や脂質が疎かになると、筋量維持・ホルモンバランス・回復に悪影響が出ます。特に筋トレ目的では、一般的な目安として「タンパク質体重×1.6〜2.2 g」程度は確保しておきたいです。
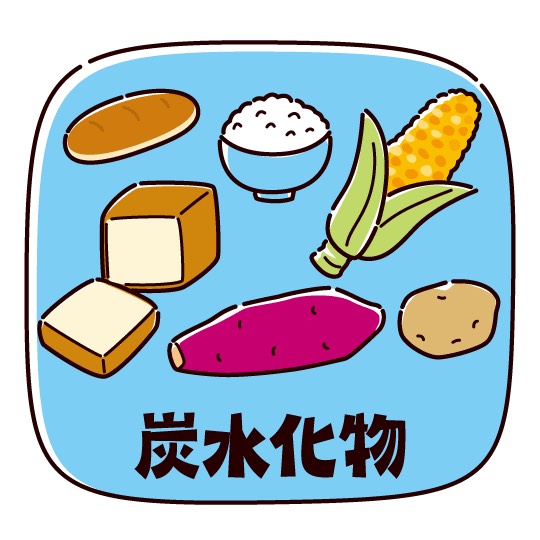
留意点・注意すべき研究的限界
• 多くの研究では「エネルギー収支(プラス/マイナス)」が結果に大きな影響を与えており、炭水化物量だけで筋量・筋力変化を語るわけではありません。例えば、「高炭水化物摂取で筋量が増えた」研究でも、エネルギー収支がプラスであった可能性が高いです。
• 抵抗トレーニングにおける「炭水化物摂取の明確な効果(筋力/筋肥大)」を示す研究は、持久運動(エンデュランス)ほど多くありません。レビューでは「通常ボリューム(10セット/部位程度以下)のセッションでは、炭水化物量の違いがパフォーマンスにあまり影響しなかった」という報告もあります。
• また、研究によって「トレーニング前・中・後の炭水化物量・タイミング」「被験者のトレーニング歴・栄養状態」「使用したトレーニングの種類(筋力 vs 筋肥大)」「エネルギー収支」など条件がかなり異なります。したがって“この量を必ずこうしなさい”という絶対値は存在しません。
• 個人差(年齢/性別/ホルモン状況/体質/トレーニング歴)があります。例えば更年期・女性・高齢者は炭水化物代謝・ホルモン環境が異なるため、個別対応が重要です。
• 炭水化物を「ただ多く摂れば良い」というのではなく、「目的(増量/減量)」「トレーニング頻度・強度」「回復状況」「脂肪量の増加リスク」を加味して調整することが重要です。
まとめ
筋トレを頑張る皆さんに向けて、炭水化物について私からのメッセージも交えてまとめておきます。
• 炭水化物は、トレーニング中の“動ける力”を支える、そして回復を助ける大切な栄養素です。特に「筋量を増やしたい」「高負荷・高頻度でトレーニングしている」場合は、ケチらず確保したいところです。
• ただし、「量=多ければ多いほど良い」というわけではありません。目的(増量/減量)に合わせて、炭水化物量・タイミング・質を調整することが鍵です。
• 増量期では、トレーニングを支えるために炭水化物量を多めに、かつ良質な炭水化物を中心に。減量期では、炭水化物量をやや抑えながら、トレーニング強度・頻度を維持できるよう工夫を。
• トレーニング前後の炭水化物+タンパク質の組み合わせは、回復・筋合成を支える有効な仕組みです。特にトレーニング後の食事・軽食は意識しておきましょう。
• そして、何より「自分の体・トレーニング量・体組成の変化を見ながら調整する」ことが最強です。毎回同じ量・同じ時間で良しとせず、「今日はセット数多かったな/疲労たまってるな/体脂肪気になるな」という日には炭水化物量を微調整していきましょう。
• 女性/更年期世代の方・高齢トレーニーの方は、ホルモン変化や基礎代謝・回復能力を考慮して、炭水化物だけでなくタンパク質・脂質・微量栄養素・休息も一緒に設計することをおすすめします。


